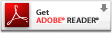薬剤部
当院薬剤部は、薬剤部長1名、主任薬剤師2名、薬剤師6名の計9名で構成されています。薬剤部の業務は、調剤業務だけではなく、入院患者さんへのお薬の服用方法や効能・効果等の説明、抗がん剤注射薬の調製、医薬品の副作用情報の収集や提供、医薬品の供給など様々な業務を行っています。
また、院内の各種チーム医療に積極的に参加し、医師、看護師、メディカルスタッフ、事務職員をはじめとする全職員と連携を図りながら、最善の薬物療法を提供しています。
関信地区国立病院薬剤師会 - Kanto-Koshinetsu National Hospital Organization Pharmacists Association (kanshinyaku.org)
また、院内の各種チーム医療に積極的に参加し、医師、看護師、メディカルスタッフ、事務職員をはじめとする全職員と連携を図りながら、最善の薬物療法を提供しています。
関信地区国立病院薬剤師会 - Kanto-Koshinetsu National Hospital Organization Pharmacists Association (kanshinyaku.org)

業務紹介
【調剤業務】

【医薬品管理業務】
患者さんに有効で安全なお薬を渡すため、購入から交付までの管理を行い、毎月の棚卸による在庫確認と院内全部の使用期限のチェックを実施しています。
また、新たに病院内で使用する医薬品については、薬剤部が事務局となって運営する薬剤委員会において採用の是非が審議されます。
【無菌調製業務】
患者さんに有効で安全なお薬を渡すため、購入から交付までの管理を行い、毎月の棚卸による在庫確認と院内全部の使用期限のチェックを実施しています。
また、新たに病院内で使用する医薬品については、薬剤部が事務局となって運営する薬剤委員会において採用の是非が審議されます。
【無菌調製業務】

【医薬品情報管理業務】
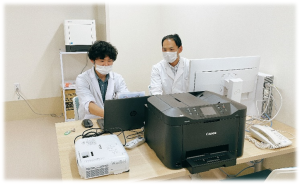
また、月に一度、新しい情報をまとめた「医薬品情報(DIニュース)」を発行し、他部門の医療スタッフに情報提供をしています。
【薬剤管理指導業務】

【治験】
当院ではⅡ相/Ⅲ相などの治験を行い、日々新薬開発に貢献しています。お薬の調製などを行い、治験が適正に行われるために準備段階から関わり、治験担当者のCRC(治験コーディネーター)に協力しています。
当院ではⅡ相/Ⅲ相などの治験を行い、日々新薬開発に貢献しています。お薬の調製などを行い、治験が適正に行われるために準備段階から関わり、治験担当者のCRC(治験コーディネーター)に協力しています。
チーム医療について
【院内感染制御チーム(ICT)】
週1回のICTラウンド、月1回の院内感染対策検討委員会やICT部会などに参加しています。インフェクションコントロールドクター(ICD)、感染認定看護師、細菌検査技師、リンクナース等と連携を取りながら、院内感染の予防に努めています。薬剤師は、院内における抗菌薬使用状況を把握するとともに、抗菌薬・消毒薬の適正使用の推進に携わっています。
週1回のICTラウンド、月1回の院内感染対策検討委員会やICT部会などに参加しています。インフェクションコントロールドクター(ICD)、感染認定看護師、細菌検査技師、リンクナース等と連携を取りながら、院内感染の予防に努めています。薬剤師は、院内における抗菌薬使用状況を把握するとともに、抗菌薬・消毒薬の適正使用の推進に携わっています。

【抗菌薬適正使用推進チーム(AST)】
薬剤耐性(AMR)アクションプランの策定により、抗菌薬適正使用が一層注目されるようになり発足しました。ICTは「感染症を起こさない・拡大させない」ことを目的として看護師が中心になり活動していますが、ASTは「感染症の診断・治療」に焦点を当て、医師、薬剤師、細菌検査技師が中心となり活動しています。週1回のラウンドでは感染症治療の観点から、個々の入院患者さんに使用している抗菌薬の適切性を検討し、主治医に寄り添う立場で助言を行っています。
【栄養サポートチーム(NST)】
入院患者さんの治療効果向上や合併症予防のために最良の栄養療法を提供することを目的とした医療チームです。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士で構成され、入院患者さんの栄養評価や適切な栄養療法の提案を疾患治療に応じて行っています。薬剤師は、高カロリー輸液や経腸栄養等の栄養剤での栄養管理やお薬の副作用による栄養障害などを確認する役割を担っています。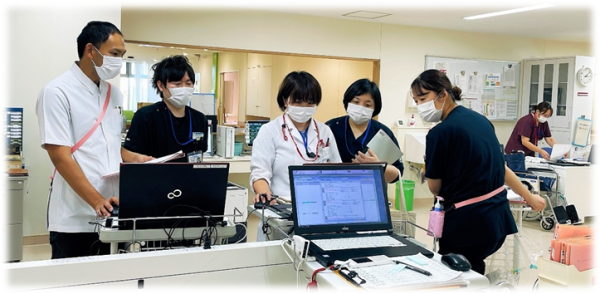
薬剤耐性(AMR)アクションプランの策定により、抗菌薬適正使用が一層注目されるようになり発足しました。ICTは「感染症を起こさない・拡大させない」ことを目的として看護師が中心になり活動していますが、ASTは「感染症の診断・治療」に焦点を当て、医師、薬剤師、細菌検査技師が中心となり活動しています。週1回のラウンドでは感染症治療の観点から、個々の入院患者さんに使用している抗菌薬の適切性を検討し、主治医に寄り添う立場で助言を行っています。
【栄養サポートチーム(NST)】
入院患者さんの治療効果向上や合併症予防のために最良の栄養療法を提供することを目的とした医療チームです。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士で構成され、入院患者さんの栄養評価や適切な栄養療法の提案を疾患治療に応じて行っています。薬剤師は、高カロリー輸液や経腸栄養等の栄養剤での栄養管理やお薬の副作用による栄養障害などを確認する役割を担っています。
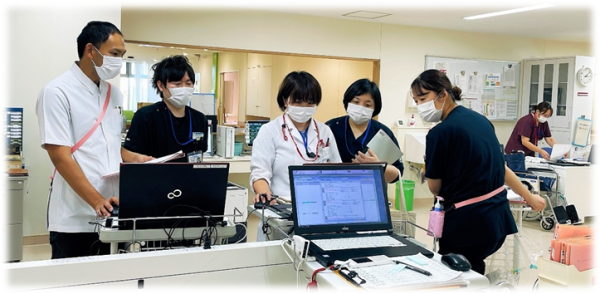
【褥瘡対策チーム】
活動性が低下したり、安静状態が長く続いたりすると、同一部位に一定以上の圧力がかかり、お尻やかかとの皮膚に褥瘡(じょくそう=床ずれ、皮膚の潰瘍)ができることがあります。また、摩擦やずれ、失禁、低栄養、やせ、加齢、基礎疾患など様々な要因も関わっています。そこで、医師、薬剤師、管理栄養士、特定看護師等で構成された褥瘡対策チームが、週1回の回診により褥瘡の予防・治療に対してそれぞれの専門性を発揮して活動しています。薬剤師は輸液や経腸栄養を用いた栄養管理や褥瘡発症・悪化に影響を及ぼす薬剤のチェックや適切な外用剤の選択に携わっています。
活動性が低下したり、安静状態が長く続いたりすると、同一部位に一定以上の圧力がかかり、お尻やかかとの皮膚に褥瘡(じょくそう=床ずれ、皮膚の潰瘍)ができることがあります。また、摩擦やずれ、失禁、低栄養、やせ、加齢、基礎疾患など様々な要因も関わっています。そこで、医師、薬剤師、管理栄養士、特定看護師等で構成された褥瘡対策チームが、週1回の回診により褥瘡の予防・治療に対してそれぞれの専門性を発揮して活動しています。薬剤師は輸液や経腸栄養を用いた栄養管理や褥瘡発症・悪化に影響を及ぼす薬剤のチェックや適切な外用剤の選択に携わっています。

【認知症チーム】
認知症認定看護師を中心として、医師等と連携し、認知症の悪化予防、せん妄対策、転倒リスクを考慮した身体疾患の治療に関して、入院患者さんが最善の治療と安心した療養生活が過ごせるように支援やカンファレンスなどを行っています。薬剤師は、薬物療法の提案、使用薬剤の整理、転倒転落リスクのある薬剤の把握を行っています。
認知症認定看護師を中心として、医師等と連携し、認知症の悪化予防、せん妄対策、転倒リスクを考慮した身体疾患の治療に関して、入院患者さんが最善の治療と安心した療養生活が過ごせるように支援やカンファレンスなどを行っています。薬剤師は、薬物療法の提案、使用薬剤の整理、転倒転落リスクのある薬剤の把握を行っています。

【緩和ケアチーム】
緩和ケアチームは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士により構成され、患者さんの様々な苦痛(身体的苦痛、社会的苦痛、精神的苦痛、スピリチュアルな苦痛)を緩和するために、一般病棟を対象に週1回のカンファレンスおよび回診を行っています。薬剤師は、麻薬をはじめとした薬剤全般の管理を行い、情報を共有して患者さんの痛みや苦痛の軽減に努めています。
緩和ケアチームは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士により構成され、患者さんの様々な苦痛(身体的苦痛、社会的苦痛、精神的苦痛、スピリチュアルな苦痛)を緩和するために、一般病棟を対象に週1回のカンファレンスおよび回診を行っています。薬剤師は、麻薬をはじめとした薬剤全般の管理を行い、情報を共有して患者さんの痛みや苦痛の軽減に努めています。

保険薬局の方へ
薬剤服用管理指導料 吸入薬指導加算に関する吸入指導報告書は下記の様式をご活用ください。